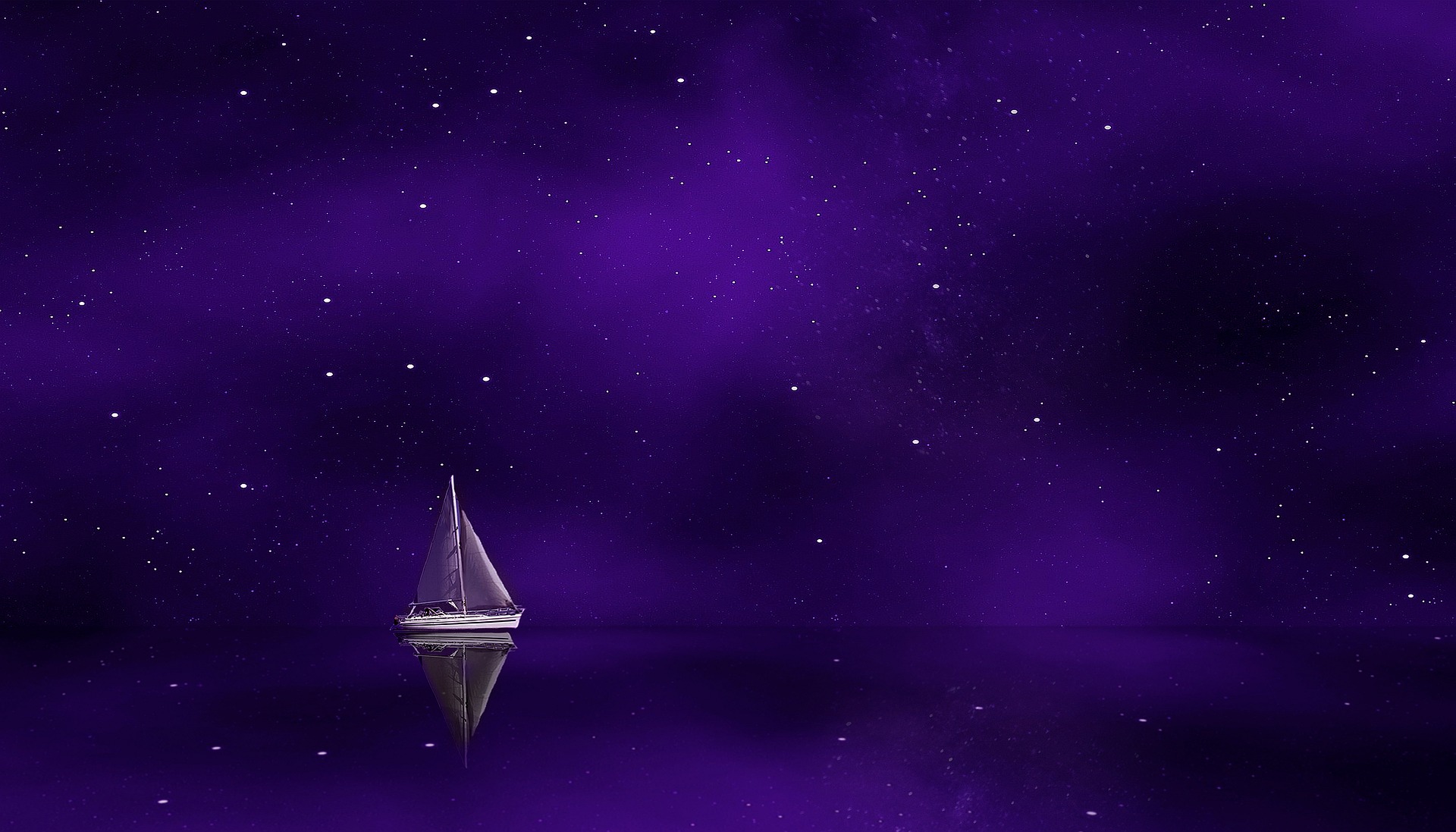今回の記事ではニーチェの言説から無意識を捉える。
フロイトもユングも、ニーチェの『ツァラトゥストラ』からヒントを得て、深層心理学の無意識にかんする理論を組み立てたことは既に明らかになっている。ユングはそれを公言して憚らなかったし、フロイトは最初は認めなかったが晩年にしぶしぶながら認めていた。
では行こう。ニーチェは楽しい。
そうだ。この自我、自我の矛盾と混乱こそが、最も誠実に自らの存在を語っている。事物の尺度であり価値たる自我、創造し意欲し価値づけるこの自我こそが。
Ja, diess Ich und des Ich’s Widerspruch und Wirrsal redet noch am redlichsten von seinem Sein, dieses schaffende, wollende, werthende Ich, welches das Maass und der Werth der Dinge ist.
上記の引用にドイツ語原文を引用したのは、[ Ich ] という言葉が「自我」と邦訳されている点に留意したいため。英訳書では [ ego ]と訳されているので自我で良いのだろうと思う。[ Ich ] は一人称の「私」としてもドイツ語で使用される。
以下の言説では、ドイツ語原文の [ Ich ] が「われ」に邦訳され、 [ Selbst ] が「おのれ」に邦訳されている。[ Selbst ] は英訳書では [ Self ] となっており一般的な邦訳では「自己」になる。ニーチェの無意識論的表現では、自我は自己に内包されない二元となっている点にも留意。ユングは、自我は自己に内包されるとした。
「われ」を意識下の自我、「おのれ」を意識の背後に広がる(肉体を含めた)無意識と考えてよい。
「われ」と、君は語り、この言葉を誇りとしている。だが、君が信じたくないと思っているもの――君の肉体とその偉大な理性の方が、ずっと偉大なものなのだ。その理性は、口で〈われ〉とは言わないが、無言で〈われ〉を実行する。
(略)
感覚と精神など、実は道具であり、玩具なのだ。これらの背後に、さらに本来の〈おのれ〉がある。この〈おのれ〉が、五感という目を使って探り、精神という耳を使って聞いている。
〈おのれ〉は絶えず聞き、かつ探る。比較し、強制し、征服し、破壊する。〈おのれ〉は支配する。それはまた、〈われ〉の支配者でもあるのだ。
わが兄弟よ、君の思考と感情の背後に、ひとりの強大な命令者、知られざる賢者がいる――その名を称して〈おのれ〉と言う。君の肉体が彼なのだ。
君の肉体には、君の最善の知恵に宿るよりも多くの理性が宿っている。何のために、君の肉体が外ならぬ君の最善の知恵を必要とするかは、誰が知ろう。
(略)
〈おのれ〉は〈われ〉に向かって言う。「ここで苦痛を感じよ!」と。すると〈われ〉は苦に耐えて、どうすれば苦の種がなくなるのかを考える。――まさにそのために、〈われ〉は考えなければならないのだ。
〈おのれ〉は〈われ〉に向かって言う。「ここで喜びを感じよ!」と。すると〈われ〉は喜びを知り、どうすればさらにしばしば喜びが生まれるのかを考える。――まさにそのために、〈われ〉は考えなければならないのだ。
(略)
創造する〈おのれ〉が、尊敬と軽蔑、喜びと嘆きを創り出したのだ。創造する肉体が、自らの意志の手として、精神を創りだしたのだ。
(白水社版 ニーチェ全集 ニーチェ著『ツァラトゥストラはこう語った』)
19世紀のヨーロッパでは精神に重い価値を置いた世相があった。ニーチェはそれに抗して「肉体の軽蔑者たち」という章タイトルを付けて上記のように語った。
「苦痛を感じよ!」の苦痛はもちろん肉体だけのことではない。精神的に打撃をうけ、悲しみ沈みこむ精神の苦痛のことも述べている。
肉体の軽蔑者たちに向かって、この章の最後には次のように語る。
君たちの〈おのれ〉は没落を欲している。それゆえ、君たちは肉体の軽蔑者になったのだ! 君たちが、最早自分を乗り超えて、創造し得ないものだから。
またそれゆえに、君たちは今や人生と大地に怒りを向ける。君たちの軽蔑に満ちた流し目には、意識されざる嫉(そね)みがある。
わたしは、君たちの道は行かない。君たち、肉体の軽蔑者らよ! わたしにとって、君たちは超人に到る橋ではない!
(同書)
初めてこの章を読む時には、〈われ〉と〈おのれ〉に混乱するかもしれない。しかしそれぞれに意識と無意識を当てはめれば完全にすっきりする。
意識(自我)とは、広大な宇宙に拡がる無意識(自己)の海に浮かぶ一隻のボートに過ぎず、そのボートは海から生まれ、海に支配され、海に命令され海に従うのである。よって超人に到る秘訣は海(無意識)にある、と解すことができる。
ユングの分析心理学の構造とほぼ同じであるが、支配するスタイルは異なる。
フロイトは〈おのれ〉に当たる無意識をエス(別名イド)と名づけ、意識と無意識にまたがる「超自我」という概念を創った。
なお、前の記事でも述べたとおり、自我については改めて考える。哲学思想的に「自我」はヨーロッパでも幾つか若干異なる概念として定義づけられているし、インドの「自我(サンスクリット語でアートマン)」はヨーロッパのそれとは全く異なる概念になる。また、仏教には自我はなく無我になる。
自己という言葉の定義にしても複数の説がある。
自分にとっての「自我」とは何かを考えるのは有意義ではあるけれど、言語的に「正しい自我」とは何かを考えるのは「真の保守」を考えるのと同じでまったくナンセンス。著者によって、あるいは文脈によって多様な語義語感があって当然だ。ヨーロッパの自我とインドの自我の違いを研究するのも良いかもしれない。
「この文脈で使用している自我という言葉はこれこれこういう定義で使用してますよ」と、ユングは丁寧に自分の定義を解説している。理系の科学者ならではの正確を期す手法だ。他方、ほぼすべての哲学者は自分の言語の定義を説明せずに書き綴っているので(しかもオリジナルの造語まで濫用して)、読者にとっては難解さの要因となるし、著者の意図から外れた誤読のオンパレードとなる。それはそれで有意義ではあるけれど。