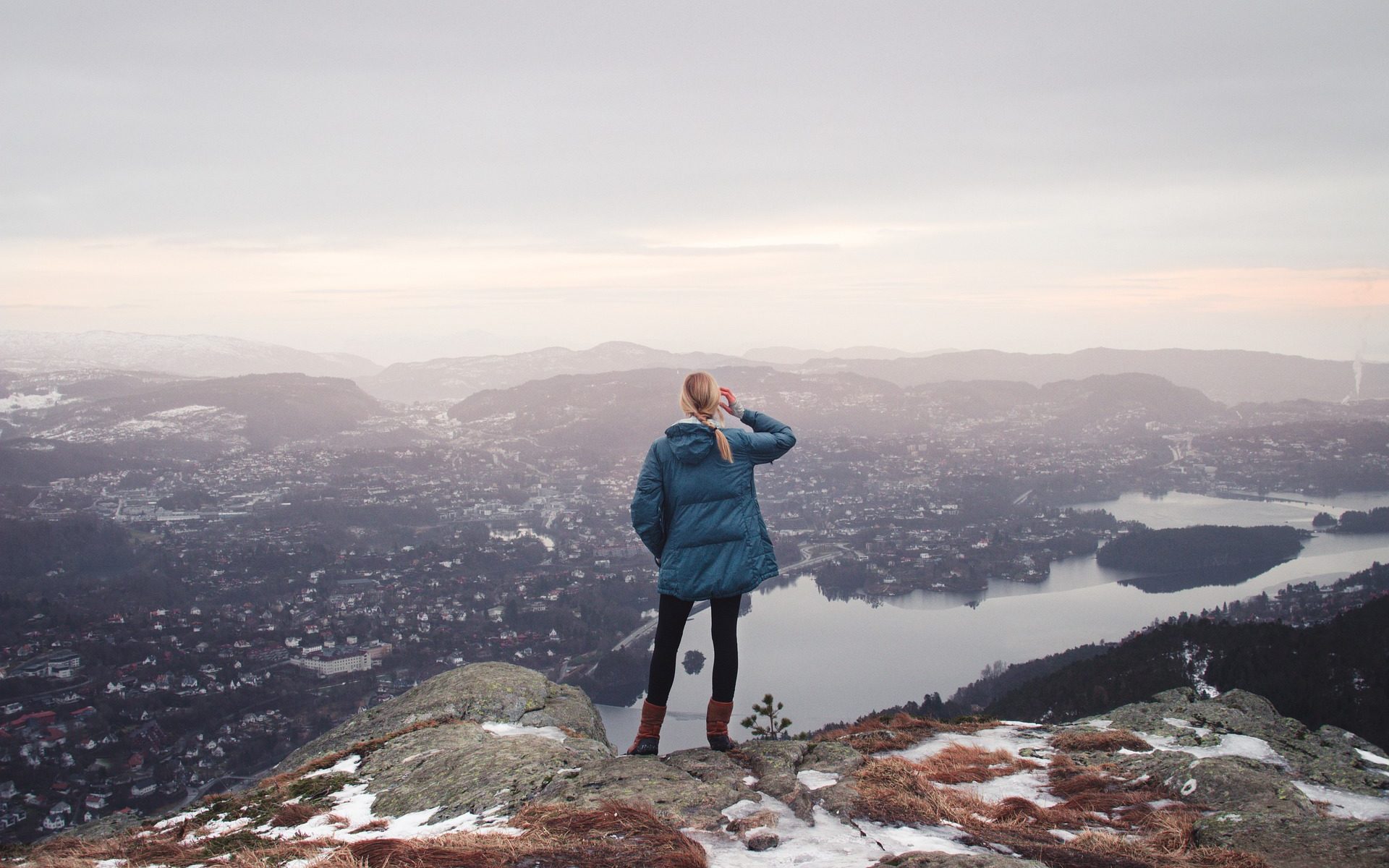昨日の断想で見てきたように、価値観には連続的同一性の性質がある。毎分毎秒、外部からの情報や内面での思索、環境や身体状態によって価値観は刻々と変化するが、分断されることなく滑らかに連続している。 そのほかの現象学的性質について、項目に分けて議論していこうと思う。 1.価値観の固有性と共有性 価値観は個人固有のものである。固有になるにはどのような... Read More
同一性
同一性について、少し考えてみよう。 自己同一性のことをアイデンティティと呼ぶことがある。この概念については以前、「帰属」を中心に断想を書いたことがある。今回は新しい視点で考える。 最も単純に、目が覚めたときの自分は、寝る前の自分と同じだと認識できるのはなぜか。それは記憶があるからだと皆言うだろう。記憶が再現されるからだと。 なるほど、では記憶とはいったいな... Read More
死を恐れないために
たとえば突然、貴方は医師から癌の告知を受けたとしよう。今それを仮定として想像するのと、現実に告知を受けるのでは迫真さが全然異なるから想像通りにはいかないと思うが、それは横におこう。 死が真に身近に迫ってくる「感じ」は、たった一人の個別体験であり、自分がいなくなることであり、真っ暗な闇の世界に物音ひとつ聞こえない。考えることができない。それも永遠に。自分が永... Read More
概念の陰翳
谷崎潤一郎の名著に『陰翳礼讃』がある。私のiPhoneには「青空文庫」のアプリがあり同書をダウンロードしてある。移動中の電車の車内で何度も読み返す率が最も高い本だ。 日本の美について、いや、日本人が何に美を見出してきたかについて、西洋文明のそれと相対比較しながらあぶりだしている。西洋は光の美であり、日本は陰翳の美である。乱暴に言ってしまえばそういう主旨だ。... Read More
概念という概念
「~とは何か?」の問いは哲学的だと言われる。私も長いあいだそう思ってきた。しかし、概念について細かく考えていくと「~とは何か?」という問いは、問い自体がおかしいのではないか?と思うようになった。 例えば、「哲学とは何か?」という問いでは哲学という「概念」を誰もが考えるだろう。ところが、7月26日の断想に書いたとおり、「哲学という概念」は普遍的なものに思える... Read More
ChatGPTとのコラボ創造
「概念論」と「価値観原理」を網羅的かつ体系的に理論化することは途方もない創造である。私独りで理論をつくるには200年かかるかもしれないと本気で思っていた。過去の哲学者たちがチャレンジしたのはそのごく一部であって、全体を体系化した理論は見たことがない。たかだか人生80年間では無理なのだ。 しかし2023年、ChatGPTというスーパー天才サポーターが登場した... Read More
概念も価値観も「今ここ」にしか存在しないのか
過去の歴史を振り返るとき、或いは過去の思想を解釈しようとするとき、まず、言語をもってその意味をとらえようとする。近世では音声や写真・映像が残っているものもあるが、それ以前を知ろうとすると文字と絵しかない。アリストテレスやカント、本居宣長らが残した文献つまり言語だけを頼りとするしかない。歴史的事実も同様にその瞬間的な事実はあっても、事実をつなぎ合わせたものは... Read More
『価値観原理』構想
昨日の『概念論』につづき、今日は『価値観原理』を理論化する構想である。 価値観の違いだとか、価値観という言葉はよく使われる。ところが、あなたの価値観を説明してくださいと質問しても、ほぼ全員の人が回答に窮する。にもかかわらず、衣食住をはじめ、学問や仕事、恋愛、結婚、個人の人生のあらゆる場面で、或いは国家などの集団社会における主義思想、政治、経済、教育において... Read More
『概念論』構想
昨年の10月15日に書いた断層。 「体系的に哲学の理論を構築する」という大構想。人間らしく懐胎から約10ヶ月間をかけてようやく産声をあげそうな気配である。 『価値観原理』と『概念論』のアウトラインを構想した。徹頭徹尾、網羅的にやる。それぞれの始原からポイエーシス的に体系化していく。 今日の断層では『概念論』の章立てを記しておくことにします。明日は『価値観原... Read More
千の顔と一つの顔
広辞苑で「洗脳」ということばを引く。新しい思想を繰り返し教え込んで、それまでの思想を改めさせること。とある。では「思想」も引いてみよう。哲学の に対する和製漢語として成立しているのでその部分を引く。判断以前の単なる直観の立場に止まらず、このような直観内容に論理的反省を加えて出来上がった思惟の結果。思考内容。特に、体系的にまとまったものをいう。とある。大辞林... Read More