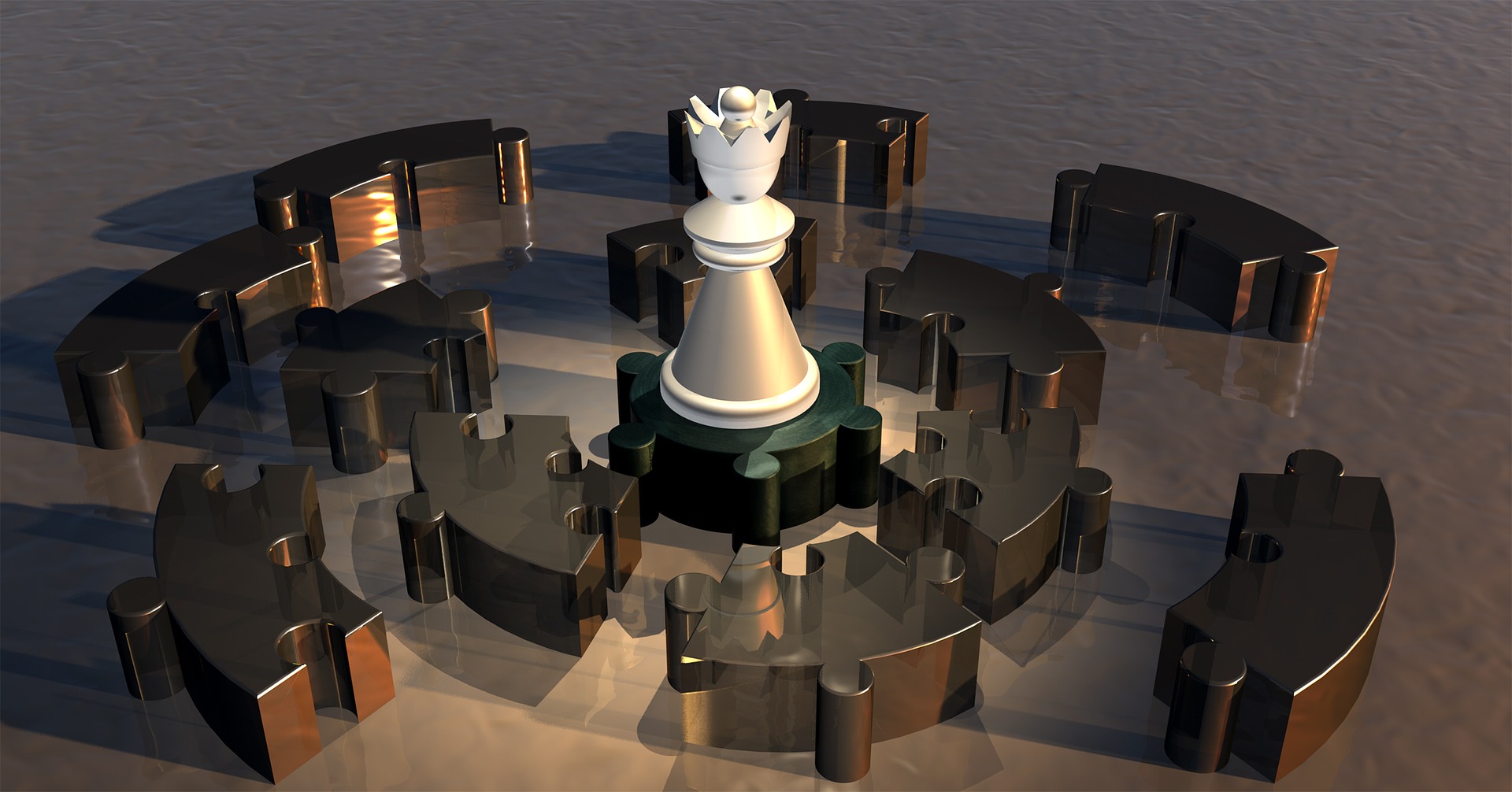subject シリーズ後半の始まりです。まずは、直接視座とはどういう視座なのかについて、例を挙げながらおさらいしておくことにします。 あなたは渋谷で友人A子さんと待ち合わせをしました。多くの人が待ち合わせ場所と利用するハチ公前です。LINEで連絡をとってA子さんは既に着いていることがわかっています。あなたはA子さんを探し10m先に見つけました。 そのとき... Read More
subject(6)第4のメタ視座
個性的で個人的な「価値」とはどのようにして生成されるのか。このメカニズムの仮説を立てることが今回のシリーズの隠れたメインテーマです。自らの中核にある価値生成に自らが意識的にかかわれるとなれば、その人は自分の人生を主体的に造作し操作することができる。言わば無意識領域を意識的に創造し調整していくことになります。メカニズムが解明されれば、ビジネスにおいても人間全... Read More
subject(5)フッサールの第三視座
西洋哲学における subject の変遷にかんしては、今回のフッサールをもってラストとします。このフッサールの第三視座こそが日本の 「subject喪失観」 と重なるものであり、subject の「後ろに控える」、コアな(中核となる)「personality(人格・個性)」および「Ego(自我)」への入り口と言えるのではないかと思います。 前の記事 の最終... Read More
subject(4)カント観念論
私たちは「認識する」という言葉をどのように使っているのでしょう。日本語の「認識」とは、“物事の本質を十分に理解し、その物と他の物とをはっきり見分けること(心の働き)『新明解・国語辞典』”とのこと。 中国語の認識にあたる言葉は単に「知っている」という意味で子どもでも使うそうです。日本語の「認識」は、中国語の意味と、西洋哲学から輸入した「(独)Erkenntn... Read More
subject(3)宗教哲学からデカルトへ
今回の記事では解り易くチャートを活用することにしました。本来は「裏に隠されたロジックの構造」にだけ目を向ければ良いのですが、哲学論の表面上にはそれを覆い隠す難解な言語があります。加えて、面倒な言い回しの数々が難解さに拍車をかける。派生する枝葉の論や歴史的背景は極力そぎ落として、「ロジックの構造」特に subject にフォーカスしてゆくことにします。 まず... Read More
subject(2)ギリシア哲学
前の記事で予告したとおり、西洋哲学の「基礎構造」を明らかにしてゆきます。 その前になぜ構造なのか、構造をどうやって明らかにするのかについて触れます。 哲学には難解な哲学用語がたくさんでてきて、それも哲学者によって語義が異なることもあり、その誤解を避けるために持論構造の説明用に新しい概念の造語を創り出した哲学者も多いです。「私の持論上でこの言葉はこの語義とし... Read More
subject(1)序
アイデンティティから続くこのシリーズですが、当初の予定では「自我について」が次のテーマでした。しかし7月一か月間の自己内議論と突如の閃きによって自我問題は矮小化されました。小さな問題になったということです。それよりも大きなテーマとして【 subject 】を掲げ、その一部として自我をどこかで扱います。 subject は哲学では「主体」「主観」と和訳されま... Read More
仮説ロジック
今日は単発記事を軽い感じで書きます。ロジック (logic) とは論理であり哲学的には論理学を指す場合もあります。古代ギリシア語のロゴス(言語)に由来する言葉です。論理的な思考のことをロジカル・シンキングと言いますよね。「どういうロジックになっているか」を考えるときは、幾つもの論理的命題がどのように繋がって全体の論理を構成しているのかが焦点となります。 本... Read More
アイデンティティ(3)
SNSの「いいね!」やポジティブコメントをもらうことは、通常、エイブラハム・マズローの承認欲求の文脈で語られる。返報性の原理(お返しをする)も混じるがこれは横に措くとして。本記事ではアイデンティティの文脈で共感や同感について考えてみたいと思う。 共感という言葉は主に感情面・感性面に使われるが、「彼の生きかたに共感を覚える」などにも使われる。一方同感は主に意... Read More
アイデンティティ(2)
さて、アイデンティティももちろん上記のロジックに関係してくるのですが、これがまた難しい。なぜ人間には「同一性」が自然にはたらくようになっているのか、その原理に嵌る価値と欲求のピースを探しているところです。 アイデンティティは「同一性」と邦訳されますが、まずは心理学的なアイデンティティではなく、哲学としての「同一性の基準」の解決を図る。 同一性... Read More