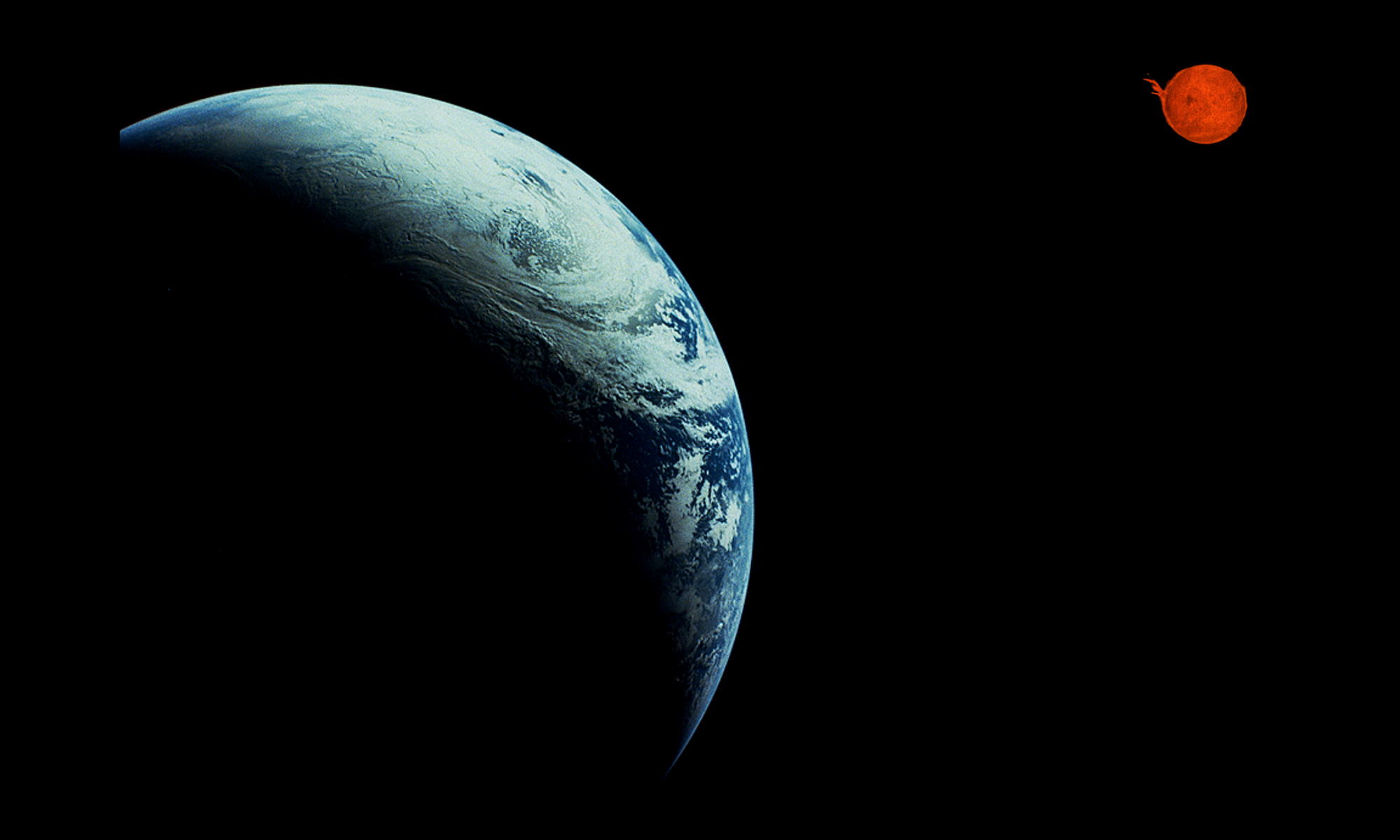〈自然〉について考察するということは、「生きる」ことについて考察することとほぼ同じだと思います。なぜ人は生きるのか。
「生くる目的は生くること也」
前回のコラムで野口晴哉氏の言葉を引用しましたが、この一文をどのように解釈すれば良いのか。その次の段落で彼が述べているとおり、ヒントは〈自然〉を知ることにあります。
ところで、私たちは昭和以降の教育を受けています。それ以前、明治維新を契機として教育の大改革が起こりました。全面的にヨーロッパの学問と教育システムを日本は採り入れました。その際に Nature の訳として「自然」があてられました。ですので、私たち現代日本人は「自然」を Nature の語義として捉えています。
それまで Nature の意味で使用していたのは「森羅万象」「天地万物」「造化」などの言葉でした。〈自然〉は「自然な」「自然に」というふうに、主に形容詞と副詞として使われており、語義が異なりました。
明治までの千年以上の長いあいだ、私たち日本人が〈自然〉として扱ってきたのは、「自然体で」とか「不自然な感じがする」などに使われる〈自然〉です。
もともとの「自然」という漢字は、紀元前500年頃、中国の『老子』第二十三章に「希言自然」、同二十五章に「道法自然」の言葉がありますので、中国から「自然」(発音はシゼンではありませんが)という漢字が(中国における)意味を伴って日本に入ってきたわけです。中国の「自然」については稿を改め、後日書こうと思います。
平安末期の辞書『名義抄』(観智院本)には「自然 ヲノヅカラ」とあり、すでに『万葉集』でも「おのずから」と訓まれていたと思われる。
(ペリカン者版 相良亨著『日本の思想』)
「自然な」の読みかたは「おのずからな」であり、「自然に」は「おのずからに」と読んでいたわけです。つまるところ、冒頭に引用した野口氏の文脈に沿っていえば、「生きる目的は生きること」を解釈するために〈自然〉を知ることが必要で、それは〈おのずから〉を知ることと同義ということです。
ただし、これはあくまで野口氏の生命論ではあるのですが。
〈おのずから〉を古典辞典で調べます。
【おのづから】
オノは、代名詞のオノ(己)。ツは、上代に用いられた、体言と体言とを関係づける連帯格の格助詞。カラは「族・柄」で、生まれつきの意。よって、物事がもともとのそのままが原義。そこから、ひとりでに、たまたま、万一などの意が派生する。(角川書店版 大野晋編纂『古典基礎語辞典』)
※現代語の「自ずから」には、〔おのずから〕〔みずから〕という、ふたとおりの読みかたがあります。〔ミヅカラ〕は「身ツカラ」が語源で、〔オノヅカラ〕から時代が少し下った平安時代から使われだしたと同辞典にあります。語釈は自分、自分自身で、主に一人称の名詞として使われていたようです。
〈おのずから〉の意味するところは、自発的(内発的)に、それ自身(その人自身)あるがままに成り行きで、意識的でなく無意識的な発露によって、必然でなく偶然に、という感じです。同辞典の同項目の語釈には「成り行きで」が二度登場しています。
次の断想は少々時間を置いて、この「成り行き」について考察したいと思っています。とても大切な〈自然〉の動きで、実は、日本人の特質が(今も)ここにあるようです。