「見る」ことそのものを問い直す、新しい身体論
このコピーライトいいと思いませんか。下記の本の帯に書いてあることばです。さて、3記事連続で書いてきましたが今回をとりあえずのラストにします。
前の記事からのつづきです。
伊藤亜紗著 『目の見えない人は世界をどう見ているのか』
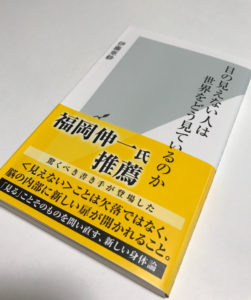
視覚障碍者に限らず、障碍をもっている人に対して私たちの社会は、「同情して接するべきだ」という空気を作りだしていると思います。これは決して間違いだとは思いません。けれど、実際に障碍がある人のなかには、同情されたくない、普通の人と同じように接してほしいと思っているが決して少なくないと、取材を通して伊藤さんはそう述べています。
むしろ、同情の空気が作りだした障碍者優先社会は、モンスター障碍者をも作りだしてきました。有名人の中には 「障碍者なのだから優先されて当たり前だろう」という傲慢な精神に陥った人もいました。
障碍ではありませんが、行き過ぎた人権主義は被害者モンスターを生みだしました。何かと言うと差別だ、人権だ、権利だ、自由だ、平等だと「叫ぶ」人が目立つようになり、ふつうはそんなモンスターに絡まれたくないわけで、不自由で形式主義的、事なかれ主義的、そうした閉塞した空気が現代社会を覆っているような気がしてなりません。皆さんはどう感じられていますか。日本に限ったことではなさそうですが。
伊藤さんは、「障害とは何か」というテーマで次のように述べます。
「障害者」というと「障害を持っている人」だと一般には思われています。つまり「目が見えない」とか「足が不自由である」とか「注意が持続しない」とかいった、その人の身体的、知的、精神的特徴が「障害」だと思われている。
しかし、実際に障害を抱えた人と接していると、いまだ根強いこの障害のイメージに対しては、強烈に違和感を覚えます。端的にいって、こうした意味での障害は、その人個人の「できなさ」「能力の欠如」を指し示すものです。「できなさ」や「能力の欠如」だから、触れてはいけないものと感じられる。
(中略)
従来の考え方では、障害は個人に属していました。ところが、新しい考えでは、障害の原因は社会の側にあるとされた。見えないことが障害なのではなく、見えないから何かができなくなる、そのことが障害だと言うわけです。
(中略)
「足が不自由である」ことが障害なのではなく、「足が不自由だからひとりで旅行にいけない」ことや、「足が不自由なために望んだ職を得られず、経済的に余裕がない」ことが障害なのです。
そのとおりですよね。すっきりと説明してもらっています。
でもひと昔前、と言っても私が子どもの頃そうだった記憶があるので半世紀も経っていないと思いますけれど、(あえて差別表現のことばで書きますが)「かたわ」の人として障碍者はレイシズム的に蔑視されていたのです。身内に障碍者がいれば世間に隠そうとした。そういう社会だった。
今もそういう目で見る人も中にはいるかもしれませんが、非常に少数でしょうし、障碍者にやさしく同情的になったことは社会の進化だと思います。そこからさらにステップアップして、「社会的生活に不都合があることを障害と呼ぶ」という意識への進化は、人格の平等性に基づく自然なふれあいだと考えます。ですので、もっとフランクに付き合っていければいいなと思います。
私が今回3記事にかけてこの本を取り上げたのは、正直に言ってしまいますが、福祉的心情はまったくありませんでした。ずいぶん前、もう何十年も前から、全盲の人の世界ってどんなんだろうという好奇心がずーっとあって、盲学校への訪問に機会を見つけて行きたいなと思っていたのです。なので伊藤さんには大感謝です。
同書からの派生で、情報を求めるのか意味を求めるのか、カクテルパーティー効果(大勢でざわついてる中から目的の人の声だけを聴くことのできる人間の能力)による「注意」というテーマができた。単なる情報ではなく意味を求める。それはフランスの哲学者アンリ・ベルクソンの「注意的再認」に当たるのではないか(運動によって情報を自然に取り込むのは「自動的再認」)とも考え、ベルクソン著『物質と記憶』を読み始めました。
知覚、記憶、想起、という人間の内部で起こっていることについて、ベルクソンの論からヒントを得、記憶とは何かについて閃いたものがあり、心の哲学の構想がなおいっそう楽しくなりました。
偶然かどうかわかりませんが、驚くことに、ベルクソンは視覚を失った場合について同書の数か所で言及しているのです。120年前の時代ですから視覚障碍者についての研究は進んでおらず(西洋でも差別されていたのかもしれませんが)、ベルクソン個人の想像です。以下に引用します。
私は、空間のなかに多数の対象を知覚する。各々の対象は、視覚的形式である限り、私の活動を促す。
私は突如として視覚を失う。おそらく私は、空間内で同じ量、同じ質の運動をなおも所有している。けれども、これらの運動は、視覚的印象に連繋させられることはもはやありえない。今後それらは、たとえば触覚的印象に従わねばならなくなるだろうし、おそらくある新たな配列が脳のなかで描かれるだろう。(ちくま学芸文庫版 アンリ・ベルクソン著『物質と記憶』)
認識論について考究してきた数多くの哲学者、カント、ハイデガー、ウィトゲンシュタインらも、「自己からの視覚的世界観」が前提にあったのではないか。ベルクソンの推測は外れました。視覚障碍者は視覚を失った後も、先天的全盲であっても、視覚的印象で世界を表象しているのです。しかも、特定の視点に固まらない全方向的な俯瞰的空間感です。
視覚は私たちに最も多くの情報をもたらす代わりに、先入観を固めてしまうデメリットがあるのかもしれません。
最後に伊藤亜紗さんのことばを引用します。
見えない人の頭の中のイメージは、見える人の頭の中のイメージよりも「やわらかい」のではないか。そう感じることがあります。
見えるとどうしても見えたイメージに固執しがちですが、見えない人は、入ってきた情報に応じて、イメージを変幻自在にアップデートできる。つまりイメージに柔軟性がある。そんなふうに思えるのです。
「見ること」に依存すればするほど、知性や感性が柔軟にはたらかなくなる可能性、あるかもしれませんね。今後の良いテーマになりそうです。
そして、「見えない」ことは欠落ではなく、別の世界の「事実」を体験していることと言える。

