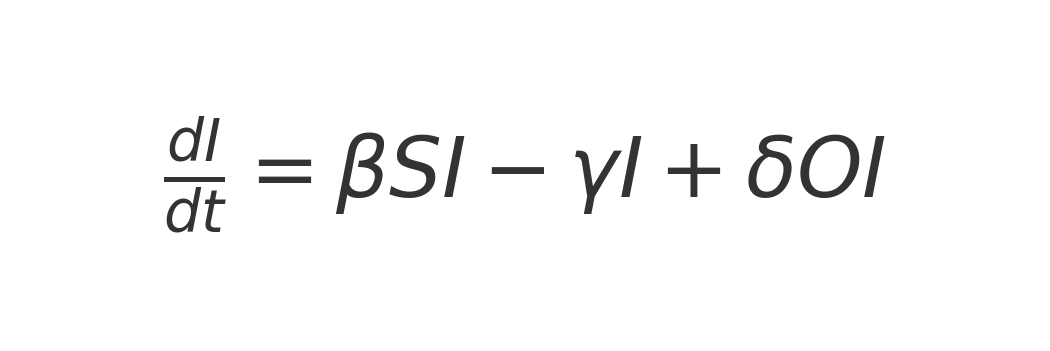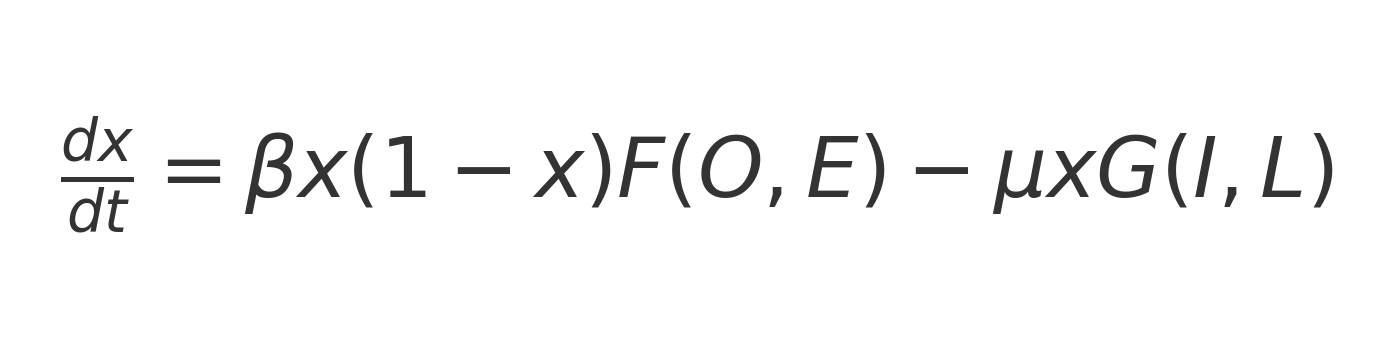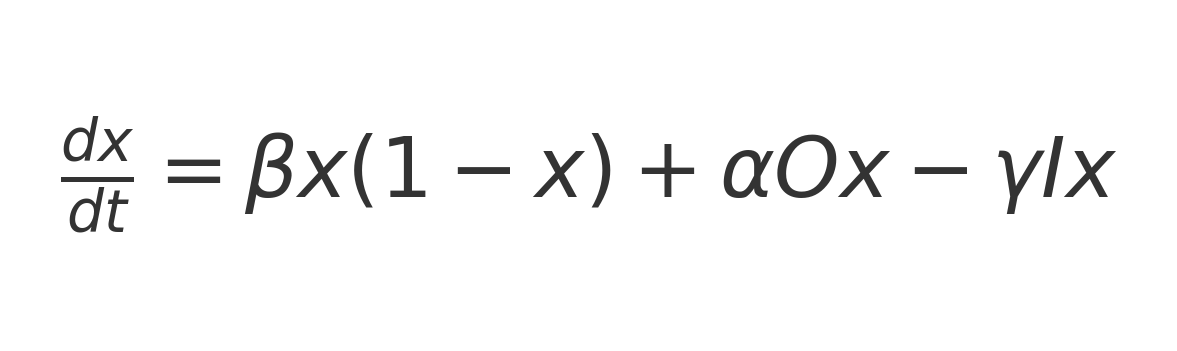寛容という概念は、社会の多様性を支える美徳として広く称賛される。しかし、現代社会ではその過剰な適用が、逆説的に害を招く場面が増えている。寛容が強制的に押し付けられ、被害者の権利が軽視されるケースは少なくない。以下では、こうした過剰な寛容の具体例を挙げ、その問題点を明らかにしていこうと思う。
近年、ハーバード大学やイェール大学、オックスフォード大学といった名門校から、一般企業に至るまで、DEI(多様性、公平性、包摂性)を掲げるポリシーが制度化されている例が増えている。ポリシー自体は脆弱な立場を守る目的をもつが、運用過程で「非寛容」と断定される基準があいまいである場合、懲戒や降格、採用差し止めといった人事的制裁につながる事例が報告されている。たとえば大学の学内委員会や人事部が、ある教員や学生の発言を「差別的」や「害悪を助長する」と判断して、調査と同時に職務排除的な措置をとるケースがある。〔※事例1〕
ここで問題となるのは、手続きの透明性や反証の機会が十分に担保されないまま即時的に処分が進む点である。
次に、学校教育での、いじめ問題の具体例を挙げる。
近年、加害者に対する過剰な寛容が、被害者を二次的に追い詰める事案を目にすることが増えた。いじめ加害者の行動を「個性の違い」や「成長過程の過ち」として扱い、被害者に耐え忍ぶことを強いる教育方針が横行している。これにより、被害者は孤立し、精神的・身体的なダメージが深刻化する。
例えば、2021年に北海道旭川市で発生した旭川女子中学生いじめ凍死事件では、被害者女性(当時14歳)が自慰行為の強要やわいせつ画像の拡散などの性的いじめを受け、凍死した。学校側は加害生徒の行動を軽視し、調査を怠り、説明会で教頭が「10人の加害者の未来が大切」と発言したことが明らかになった。〔※事例2〕
この過剰な寛容は、加害者の更生を名目に被害者の救済を後回しにし、学校という空間の安心を崩壊させる。文部科学省の報告でも、いじめ認知件数は増加傾向にありながら、加害者への厳格な対応が不足している事例が散見される。結果として、子どもたちの信頼関係が損なわれ、教育現場全体の規範が揺らぐことを招いた。もちろん、学校側の保身の一面は少なからずあるだろうが、ここで問題としているのは「寛容」の免罪符的側面である。
寛容は容易に権力の道具へと転用される性質を持つ。寛容という高潔な言葉が政治的レトリックに取り込まれると、基準を定める主体が恣意的な力を行使できるようになる。特定の価値観を「寛容の主流」として確立することで、対立する文化や意見を持つ人々を「不寛容」と烙印し、社会から排除することが可能になる。
こうした言論権力の行使が、手続き的正義や法の下の平等を蝕み、結果として社会的分断を深める。寛容が倫理的免罪符として使われるとき、その道具化は被害を見えにくくし、公共の議論を貧しくする。この道具化は、規範の名の下に寛容を強いる構造を生み、結果として安心の基盤を揺るがす。
また、寛容を掲げる側が道徳的優越感に陥ることも問題を大きくする。自らを「寛容な側」と位置づけることで、相手を容易に道徳的に裁断し、吊るし上げる論理が働きやすくなる。
これが「高潔さの独善」であり、寛容の語が逆に不寛容を正当化するパラドックスを生む。被害を訴える当事者であれ、反対意見を唱える学者であれ、寛容なる社会規範の中で瞬時に抹消されうるという不均衡が生じると、公共性の場は安全な討論の器ではなく、感情的な裁判所へと変質する。
最後に制度設計の難しさについて述べる。寛容を守るために用意した仕組みが、同時に寛容を侵食することがある。表現の自由を守る法制度が、被害を受ける集団の安心を奪うこともあり得る。こうした価値間の衝突は容易に一義的な解を持たず、制度は永続的な調整と再検討を前提に設計される必要がある。寛容を成熟させるということは、単に美徳を称揚するのではなく、その運用と帰結を慎重に見通し、手続き、救済、説明責任を組み入れていく営為を意味する。
擁護者は「寛容は社会の多様性と創造性の基盤であり、否定すべきでない」と主張するだろうが、その主張を受け止めたうえで強調したいのは、問題は「寛容を否定するか」ではなく「寛容をどう設計し運用するか」に尽きるという点である。
こうした批判を踏まえ、自由・寛容・規範・安心の相互力学の全体構造を明らかにし、自由と同様、寛容も条件つきの実践として再設計する必要がある。
しかし私は、どのような寛容が良いのかという「善」や「正しさ」の社会的価値観には踏み込まない。ゆえに実践としての再設計を行わなず、他者の手に委ねたい。もっぱら、自由・寛容・規範・安心の相互力学の全体構造を明らかにすることにつとめる。
〔事例1〕
大学・企業におけるDEI政策と寛容批判
参考資料1 要約
-
- Yale大学 — 教員Bandy LeeがTwitter上でトランプ前大統領らの精神状態について発言後、大学は「専門職倫理違反」と判断して契約解除。発言の自由と大学倫理基準の衝突をめぐる訴訟へ発展。
- Oxford大学 — 大学のハラスメント/SNSガイドラインが「敬意を払う」といった曖昧な基準を義務化。学者たちは「合法的な発言が処罰対象となる」と懸念を表明。
- Harvard大学 — DEIタスクフォース設置後、学生から「差別や嫌がらせに対する保護が不十分」との声が上がる一方、自由な発言の抑制を指摘する意見もあり、学内で対立が深まる。
- 企業分野(ソフトウェア工学) — DEIへの反動を示す研究。制度化が摩擦を生む事例。
参考資料2 リンクURL
-
- ABA Journal (2021): “Yale prof claims she was wrongly fired after tweeting about Trump, Dershowitz, and shared psychosis”
https://www.abajournal.com/news/article/yale-prof-claims-she-was-wrongly-fired-after-tweeting-about-trump-dershowitz-and-shared-psychosis - The Standard / PA News (2022): “Oxford University harassment and social media policies may inhibit lawful speech, academics warn”
https://www.standard.co.uk/news/uk/oxford-university-indian-instagram-b1005349.html - Cherwell (2025): “Oxford disciplinary statute changes spark free speech concerns”
https://cherwell.org/2025/06/04/oxford-disciplinary-statute-changes/ - The Harvard Crimson (2024): “The Fight Over DEI Arrives at Harvard”
https://www.thecrimson.com/article/2024/2/24/dei-scrut/ - arXiv (2025): “The Tech DEI Backlash: The Changing Landscape of Diversity, Equity, and Inclusion in Software Engineering”
https://arxiv.org/abs/2506.14232
- ABA Journal (2021): “Yale prof claims she was wrongly fired after tweeting about Trump, Dershowitz, and shared psychosis”
参考資料3 反論
一部の記事および報告では、DEIプログラムは批判されつつも「完全に言論を抑圧する装置ではない」と論じている。むしろ制度内外で調整や対話が進み、持続的に運用されている点に注目すべきだとされる。たとえば「Harvard’s DEI Complex Is Stronger than Ever」は、制度が批判や反動に直面しても依然として強固であり、崩壊や全面的な縮小には至っていないという見方を提示している。
https://manhattan.institute/article/the-harvard-dei-complex-is-stronger-than-ever?utm_source=chatgpt.com
〔事例2〕
旭川女子中学生いじめ凍死事件
参考資料1 要約
- 事件概要: 2021年2月13日未明、旭川市立北星中学2年の女子生徒(当時14歳)が自宅を出たまま行方不明となり、同年3月21日に同市内の公園で凍死体で発見された。検死で死因は低体温症(凍死)と判定された。
- いじめの報道と調査開始: 文春オンラインは、被害生徒が2019年に別の中学校で上級生から性的ないじめ(わいせつ行為の強要)を受け、その後学校対応が不十分だったと報じた。これを受け、市長は「大きな疑念が広がっている」として教育委員会に第三者調査を指示し、事実確認に乗り出した。
- 加害内容: ビジネスジャーナル(2021年4月)などは、上級生グループが被害生徒にわいせつ動画の撮影を強要し、画像をSNSで拡散するなど凄惨ないじめを報じた。当初、学校側は「男子生徒らのいたずらに過ぎない」と説明し、対応が杜撰(ずさん)だったと伝えられている。
- 学校・教育委員会の対応: 2021年8月30日、市教育委員会が記者会見で調査状況を説明し、教育長は遺族対応について「一つ一つの取り組みをより丁寧にしたい」と述べた。その後、第三者委員会は2022年9月にいじめの存在を認定し、「いじめがなければ自殺は起こらなかった」と結論付けた(注:再調査で認定)。
- 謝罪と公式見解: 2022年4月8日、第三者委報告を受けた旭川市議会で黒蕨教育長が謝罪し、「いじめを認知できなかったことを深く反省し、お詫び申し上げます」と遺族に謝罪した。これにより市教委は公式にいじめの存在を認め、再発防止策を検討している。
参考資料2 リンクURL
- NHK北海道ニュース「女子中学生の死亡 報道受け“いじめ”調査へ 北海道 旭川」(2021/4/22) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210422/k10012991091000.html
- Business Journal「旭川・中学生いじめ自殺、校長のおざなりな対応露呈…市教委・警察は『いじめ』認識」(2021/4/19)
https://biz-journal.jp/journalism/post_221101.html - 朝日新聞「遺族に『より丁寧に対応』 いじめ調査で旭川市教育長」(2021/8/31)
https://www.asahi.com/articles/ASP8Z77GLP8ZIIPE01Z.html - 朝日新聞「旭川中2女子凍死、教育長が遺族に謝罪 第三者委がいじめ認定で」(2022/4/8)
https://www.asahi.com/articles/ASQ48564DQ48IIPE00Z.html
参考資料3 反論
- 共同通信配信(2025年8月24日付)では、当時の中学校校長であった金子圭一氏が記者集会で「再調査委報告には事実誤認がある」と主張し、加害生徒とされた子どもたちも「過剰な報道」や中傷の被害に遭ったと述べているnews.jp。
- 月刊『北方ジャーナル』(2024年11月号)は、本事件に関する大手メディア報道に「事実と異なる記載」があったと指摘し、市教委の最初の第三者報告書で多数の記載が黒塗りにされた点など、真相が隠蔽されていた可能性を報じているhoppo-j.comhoppo-j.com。