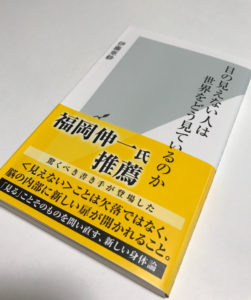今日の記事は自分で言うのもなんですが、注目記事です。人によっては後頭部をハンマーで殴られたようなショックを受けるかもしれません。(中にはその本読んだよ~という人もいらっしゃるでしょうけれども。)
2月6日に書いた記事(これも人気記事でした) 『絶対的空間感と相対的空間感』 のなかで私は、方向音痴の人は絶対的空間感をイメージできないのではないかと書いたのですが、私の周囲の人に聞き込み調査をした結果、とりあえずはそのとおりでした。(カーナビが無い時代に)自動車を運転して目的地に到着できない、地図と目視の動的混合ができない。地図を読もうとするときに、地図を動かして自分目線の方向を上にするという特徴も共通していました。自分が動く場合に、空間の方を固定したイメージを作れないようです。
ですが逆に私は、「動的メタ認知をイメージできない」という世界をイメージできないのです。お互いさまなのです。
そして同記事の中で、次のように私は書きました。
盲目の人の立場になれば、彼らは脳内で自分が今いる周囲を「相対的」空間イメージとして感覚していると同時に、「絶対的」空間イメージとしても感覚しているとしか思えない。機会があれば聞いてみたいと思う。
自分で聞くことはまだできていませんが、同じように「全盲の人の世界観てどんなんだろう」という好奇心を持たれるかたがやはりいて、そのかたが取材・考察して著した本を数日前に見つけ手にしました。
予想どおりと言いますか、予想以上です。
結論から言いますが、全盲の方の世界観は、自分自身を起点としていません。世界は自分がいる位置から開闢していないということです。しかも驚くべきは、なおかつ、視覚的世界観をイメージしているのです。
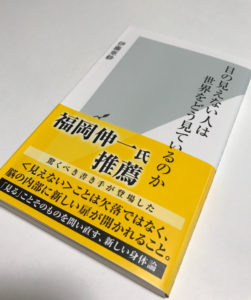
光文社新書版『目の見えない人は世界をどう見ているのか』
序章 見えない世界を見る方法
第1章 空間
第2章 感覚
第3章 運動
第4章 言葉
第5章 ユーモア
著者 伊藤亜紗(1979-)
東京大学文学部卒、同大文学博士、専門は美学、現在は東京工大リベラルアーツセンター准教授の職にあるかたです。
美学とは何ぞやと思うかたのために序章より伊藤さんの言葉を引用します。
美学とは、芸術や感性的な認識について哲学的に探究する学問です。もっと平たくいえば、言葉にしにくいものを言葉で解明していこう、という学問です。
右脳で展開されている世界を左脳で語る、ようなイメージだと私は受け取りました。難しいジャンルだと思います。
視覚障碍者のかた数名とその関係者のかたがたに密着取材しています。視覚障碍者のためのワークショップやフォーラムにも積極的に参加されています。
序章にある次の言葉は特に強調しておきましょう。
視覚を遮れば見えない人の体を体験できる、というのは大きな誤解です。それは単なる引き算ではありません。見えないことと目をつぶることとは全く違うのです。
視覚障碍者のかたがたへの礼(尊重)ですね。理解に近づくことはできても完全に理解することはできないという心得だと思います。
つづけて同書 第1章「空間」より引用します。
私と木下さん(※視覚障碍者のかた)はまず大岡山駅の改札で待ち合わせて、交差点をわたってすぐの大学正門を抜け、私の研究室がある西9号館に向かって歩きはじめました。その途中、十五メートルほどの緩やかな坂道を下っていたときです。木下さんが言いました。
「大岡山はやっぱり山で、いまその斜面をおりているんですね」。
私はそれを聞いて、かなりびっくりしてしまいました。なぜなら木下さんが、そこを「山の斜面」だと言ったからです。毎日のようにそこを行き来していましたが、私にとってはそれはただの「坂道」でしかありませんでした。
(中略)
人は、物理的な空間を歩きながら、実は脳内に作り上げたイメージの中を歩いている。私と木下さんは、同じ坂を並んで下りながら、実は全く違う世界を歩いていたわけです。
私は、全盲の人というのは相対的空間観(自己視点)と絶対的空間感(俯瞰視点)が半分半分くらいなのかなと想像していましたが、なんと、ほぼ絶対的空間感だけをイメージしており、それも晴眼者(視覚に障碍が無い人)が想像しえないハイレベルの三次元空間感が彼らの世界なのでした。
視覚に入ってくる光景を私たちは立体的に脳で変換していますが、実際には表面上の一面しか見えておらず、見えているモノの裏側や隠されている残りの大部分を想像によって補い立体化しています。立体的リアルがそこにあるように思い込んでいるだけです。
視覚障碍者の場合は、「自分はイメージを作っている。」という自覚があるのです。ここの柔軟性が決定的に違うのだと思います。
続けて引用します。
たとえば「富士山」。これは難波さん(視覚障碍者のかた)が指摘した例です。見えない人にとっての富士山は、「上がちょっと欠けた円すい形」をしています。いや、実際に富士山は上がちょっと欠けた円すい形をしているわけですが、見える人はたいていそのようにとらえていないはずです。
見える人にとって、富士山とはまずもって「八の字の末広がり」です。つまり「上が欠けた円すい形」ではなく、「上が欠けた三角形」としてイメージしている。平面的なのです。
(中略)
三次元を二次元化することは、視覚の大きな特徴のひとつです。「奥行きのあるもの」を「平面イメージ」に変換してしまう。(中略)もちろん、富士山や月が実際に薄っぺらいわけではないことを私たちは知っています。けれども視覚がとらえる二次元的なイメージが勝ってしまう。
(中略)
見える人は三次元のものを二次元化してとらえ、見えない人は三次元のままとらえている。つまり前者は平面的なイメージとして、後者は空間の中でとらえている。
だとすると、そもそも空間を空間として理解しているのは、見えない人だけなのではないか、という気さえしてきます。
(中略)
なぜそう思えるかというと、視覚を使う限り、「視点」というものが存在するからです。視点、つまり「どこから空間や物を見るか」です。
上記の記述に続いて、視覚障碍者のかたがたには特定の視点がなく、自由自在にイメージしていること、イメージしたものに表と裏はなく、驚くべきことに建造物(書では太陽の塔を例に挙げています)の内部と外部も等価としてイメージしていることが述べられています。
表と裏が無いというのは何となくイメージできます。内部と外部が等価というのはなかなかイメージしづらかったのですが、スケルトン構造のイメージではないかと思います。
もちろん、視覚障碍者としてひとくくりにはできません。著者の伊藤さんも慎重に書いています。先天的に全盲のかたと、病気や事故によって全盲になってしまったかたの違いは大きいでしょうし、イメージ自体も個別に違っていて当然だと思います。なにしろ晴眼者であっても、私とあなたではイメージしている世界の数や世界観の質感、時間感、情感、世界観の混合の仕方なども違ってあたりまえだからです。
つまるところ、「人は~」として人間をひとくくりにして普遍的に、認識論や存在論を語ることはできない、或いは限界が浅いところにあるということではないでしょうか。どれほど有能な哲学者や科学者でも、自分のイメージ上でしか観念世界を語りえない。認識メカニズムの理解は個人的経験に基づく仮説の域を出ることはない。
晴眼者にとって天動説(自己視点)のイメージは簡単ですが、地動説(三次元空間の俯瞰視点)の今まさに動いているイメージの世界観(自分もその中で動いていて、世界も動いている感)は、個人差が大きいのではないかとも思います。メタ認知の自他の差があるということについては、互いに認めあうべきだと思います。
もう一度引用しておきます。
私と木下さんは、同じ坂を並んで下りながら、実は全く違う世界を歩いていたわけです。
なお同書の今回の引用は、第1章の「空間」です。(続きで気になるところがあればまた記事に書くかもしれません)
第1章の小テーマでは他にも魅力的な内容がたくさんあります。
「私が情報を使っているのか、情報が私を使っているのか」「踊らされない安らかさ」「視野をもたないがゆえに視野が広がる」「視覚がないから死角がない」 など。
晴眼者が情報をインプットする場合、その五感感覚は視覚によるものが80~90%だそうです。全盲のかたがたは私たちよりもはるかに少ない情報量で世界を把握していることになる。想像力が抜群だということです。創造力の根源は想像力ですので、全盲のかたがたはクリエイティブの才能が豊かなのかもしれません。なかなか発掘されていないだけで。
私たち晴眼者の世界では、文明の発達によってテレビや映画、最近では3DどころかVRの世界までをも科学が作りだしました。機械はどんどんクリエイティブに進化していくのと反比例して、人間の想像力はどんどん劣化していくのです。VRを見るよりも、映画やテレビを鑑賞するよりも、小説を読んだ方がイメージを自由に飛翔させることができ、はるかに想像力が身につくのにもかかわらず、それをしない現代人が増えているように思います。
逆に言えば、目を閉じてクラシック音楽でも聴きながら、架空でも現実でもよいので世界観をイメージし、物語を映像的に脳内だけで創作してみる。視覚主体の思い込みからの自己解放、そこから何かが生まれてくる可能性がある。この本を読んでいてつくづくそう考えるようになりました。