内向と外向について考察してみようかと思った今回ですが、気づいたことがあるので先にこちらを。といっても例によって閃きの段階なのですが。
まずユングの分析心理学のロジックを方程式的にまとめる。
〇統合人格(パーソナリティ)=意識+無意識
〇人格の機能→心の構え=意識の構え+無意識の構え
※容量およびエネルギーのイメージ。私としては、意識1:無意識1000、をとりあえずイメージする。おそらくこれ以上に無意識は膨大だ。科学で解ること:科学で解らないことも同様だと思われる。
〇意識の構え→ペルソナ※内省的に自覚しようと思えば自覚できる
〇無意識の構え→アニマ(またはアニムス)※無自覚であり自覚できない
〇統合人格の構えーペルソナを生成する構え=アニマを生成する構え
〇ペルソナ変更→(影響)→アニマ変更→(影響)→統合人格変更
〇アニマ変更→(影響)→統合人格変更→(影響)→ペルソナ変更
〇統合人格の変更→機能の変更→意識の構えの変更→ペルソナの変更
〇統合人格の変更→機能の変更→無意識の構えの変更→アニマの変更
(※参考)最終的にユングはペルソナとアニマの統合を提唱する。しかし自分自身を実験台にしたがこれはうまくいかなかったようだ。成果について述べていない。私はユングのペルソナ+アニマの統合論を支持しない。
意識できるのはペルソナだけである。論理的には、優先機能の変更を行うことが可能であれば、構えを変更することでペルソナを変更できる。統合人格を変更できる。(前の記事)
さてここで、逆に、ペルソナを変更すれば意識の構えも無意識の構えも変更できることに気づく。しかしペルソナは構えの変更なしに変更できない。
西洋的手法であれば頭(理性)で考えて変更を試みるのだろう。例えば瞑想をする際に(アメリカではメディテーションが流行りらしい)「雑念を振り払おうとする」のであるが、これはできない。やはり西洋流では意識的に心の機能を変更するロジックでやるほかない。
ところが日本流であれば体の型を整えることで「雑念は勝手になくなる」となる。雑念がなくならないのは体の型が悪いとなって、禅寺の座禅では警策で打たれるのだ。
何を言いたいのかを直截にいえば、日本の礼儀作法はそれ自体に本質的意味はなく、礼儀作法の型に体を整えることを一種のセレモニー(機会的意義としての儀式)として無意識の構えを直接的に動かし、ごく自然に、無意識のほうを変更しているのではないかという推論的仮説である。
なにしろ無意識には世界創生からの歴史が遺伝に組み込まれており、この地に生を受けてから今までの情報と智恵と反応等が、頭脳と肉体に蓄積されているのだ。今この一瞬に二つのことさえ同時に頭に思い浮かべることのできない意識の小ささと比較すれば、無意識のほうが圧倒的に膨大な領域を占め、巨大なエネルギーを蓄えている。この重要性は現代ならば知性として理解できるが、古代日本人の知性では理解できず、非合理の直感として大切に扱ってきたのではないのだろうか。
例えば日の丸の国旗が掲揚されるのを見るとき、そこで愛国心(意識)へ振れるのではなく、機会として無意識の構えが発動されるほうの意義である。すると意識の構えも変わり聖たる厳粛な気持ちとなって(おそらく)自分の顔の表情も変わってくる。
スポーツで重要な試合のとき「集中!」はよく言われる。野球であればボールに集中する。これはけっして間違いではない。が、精神の集中を意識すればするほど体は固くなる。体をリラックスさせつつ精神を集中させることは意識的にできない。ゾーン状態に入るのは、集中とは真逆の意識の放散である。無意識にすべて任せる。左脳を遮断する。
イチロー選手が打席に入ると皆が知っての通り、ピッチャーが構えに入る前にルーティンのセレモニーを行う。それも一球一球必ずだ。彼は集中力を高めているのだろうか。そうではなく逆に放散し、体が覚えている反射・反応にすべてを委ねる無意識の構えを意図的に造りだしていると私は考えている。あのルーティンセレモニーを「機」として。
本記事に関連すると思われるプラシーボ効果という、社会心理学で確立された現象がある。あくまで「現象としてある」が定説になっているだけで、科学的に原理が解明されたわけではない。手がかりすらつかめていない。
次の記事ではアンリ・エレンベルガー著『無意識の発見』から、現代でプラシーボ効果と呼ばれている現象を、西暦以前から意図的に活用してきた歴史を少し振り返ってみたい。無意識の構えを「セレモニーによって造る」ヒントになるかもしれない。いずれにしてもセレモニーをルーティン化して無意識に染み込ませなければ、たった一回初めてのセレモニーでどうこうなるわけではないだろう。
セレモニーの、意味ではなく機会としての意義を見直してみる。
これは今後の大きなテーマですが、意識的な「自然体」をはるかに超えた、無意識的な「超自然体」へ近づくには、西洋の合理的論理的思考だけでは不可能だと思います。日本の非合理的直観の歴史に糸口を見いだせるような気がしてなりません。わくわくしてきます。



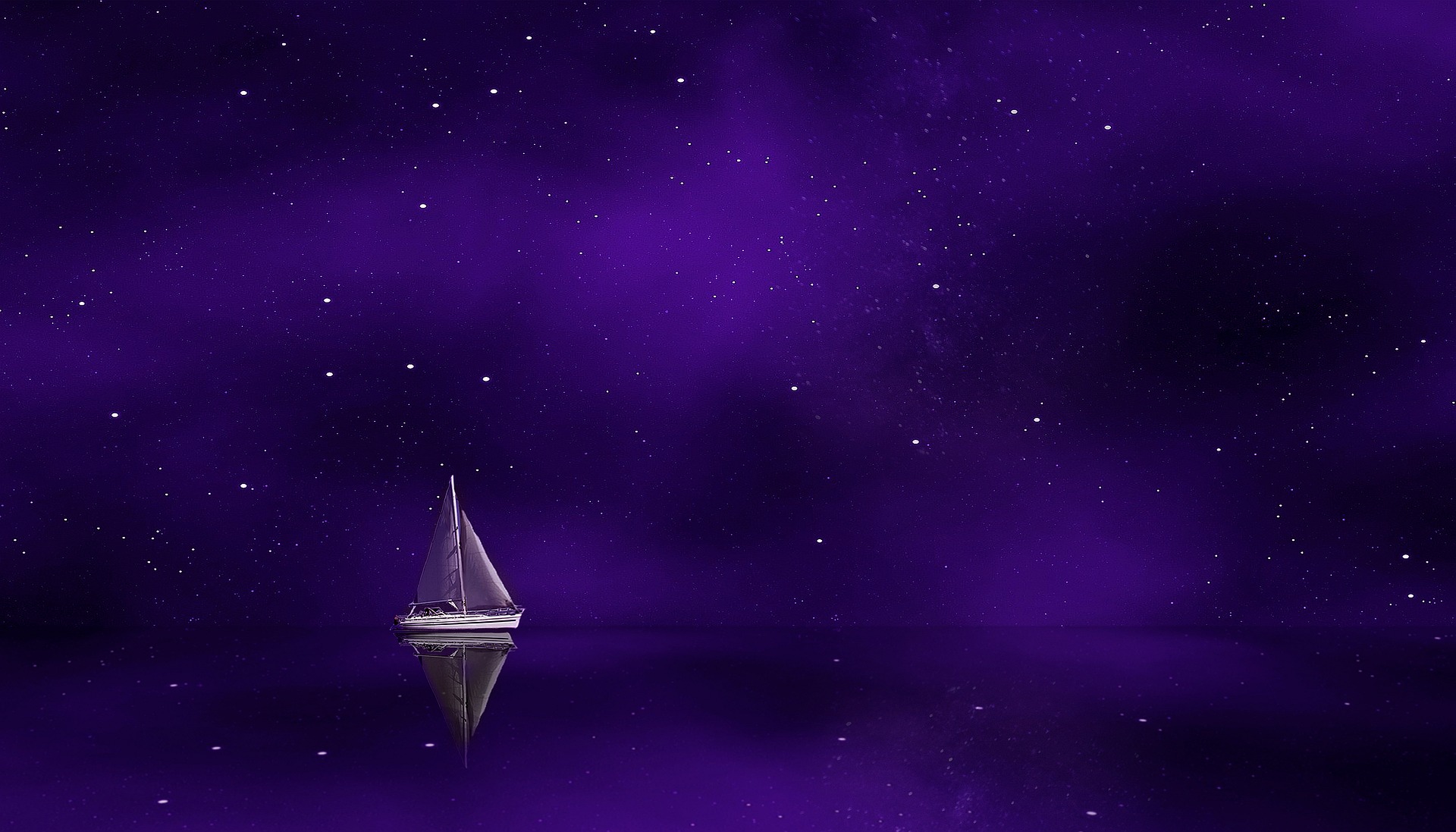




 無意識を探究し新しい理論を構築するためには、偉大な先賢たちが研究したロジックを参考に学ぶのが良いと思っている。
無意識を探究し新しい理論を構築するためには、偉大な先賢たちが研究したロジックを参考に学ぶのが良いと思っている。 私はこの『タイプ論』がユングの主著として相応しいと思っている。無意識を研究するための理論がしっかりしているのだ。ある意味、哲学書でもある。
私はこの『タイプ論』がユングの主著として相応しいと思っている。無意識を研究するための理論がしっかりしているのだ。ある意味、哲学書でもある。


