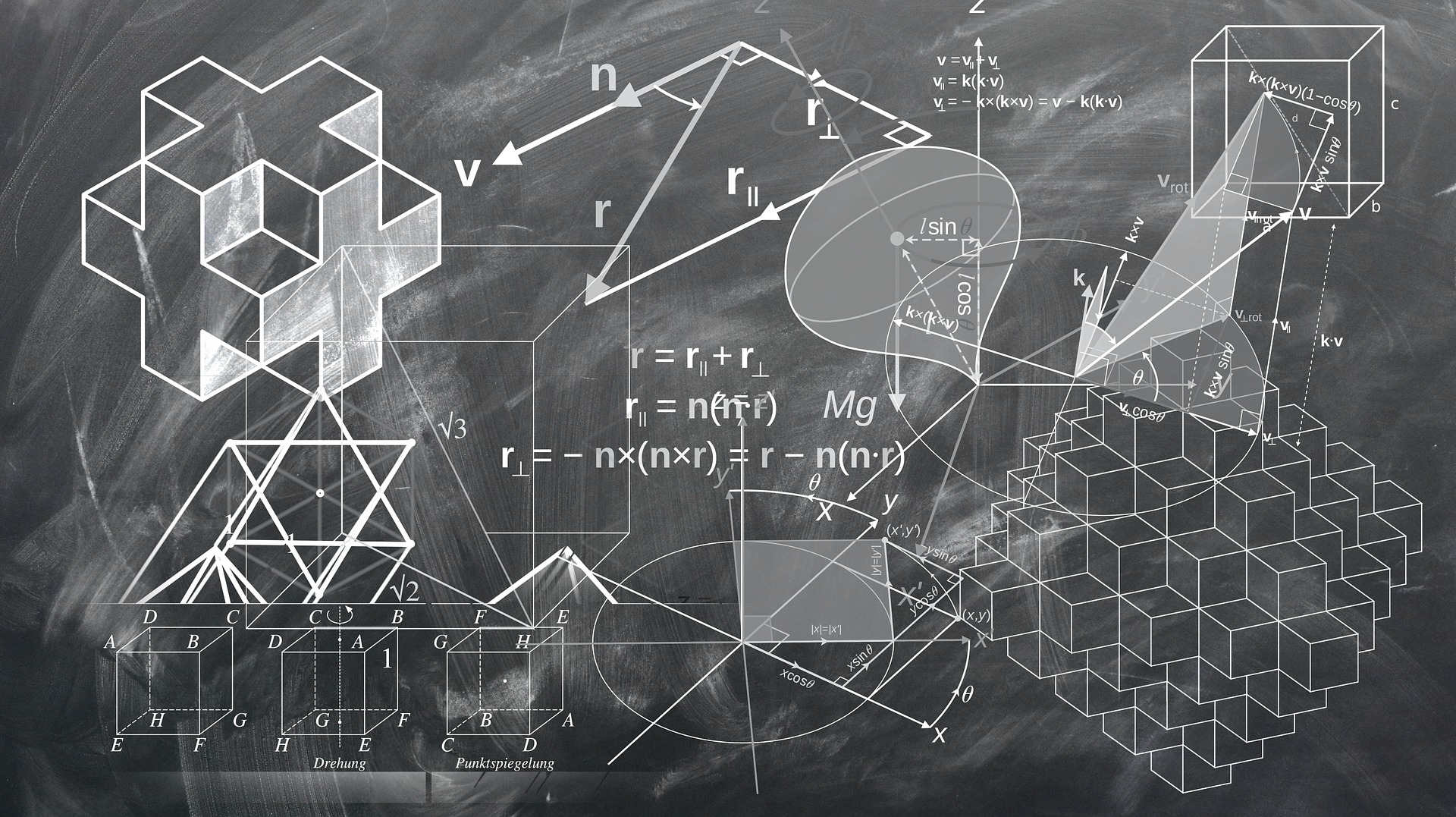《断想》を書くのはひさしぶりだ。約三か月ぶり。最近はインプットがほとんどでアウトプットが出来ていなかった。サボりだ。インプットは楽だからねえ。でもインプットだけでは全然身につかない。忘れてしまう。あまり意味がない。本来、アウトプットのためのインプットのはずだ。読書で学んだことを使っていくことで、はじめて身についていく。そういうものだろう。 ところで、このウ... Read More
巨人の肩の上には乗らない
知の創造にはオリジナルなどなく、先人たちが積み重ねてきた業績を土台として展望を開いてきたという思想がある。進歩主義思想である。先人たちを「巨人」として喩え、我々は巨人の肩の上に乗って遠望することができるなどと言う。ニュートンが述べた言葉とされる。 ゼロから知の創造を立ち上げることなどできないと、まるでそれが真理かのように語る人がいるが、自分が進歩主義思想の... Read More
人生フィナーレの思想
「どのように生きればよいのか?」「どう生きようか?」 この問いが頭のなかを駆けめぐるという経験をしたことがない人は滅多にいないだろう。誰もが考えること。高齢になってもこの問いを考える人がいるかもしれない。一方で、ある程度の年齢を超えると「どう死のうか?」を考えるようになる。このことを考えない人考えることを避ける人もなかにはいるだろう。 「どう死のうか?」は... Read More
本格的なライフワークとして
このウェブサイトの二つの柱である『人類哲学の独創』と『私の美学建設』を創っていくことは、私のライフワークとなった。ライフワークにしようと目的化したのではなく、いつしか自然にそうなった。 「ライフワーク」 を辞書でひくと次の意味が出てくる。 一生をかけてする仕事や事業。畢生の仕事。(広辞苑第六版) 一生をかけた仕事や作品。畢生の事業。(大辞林第三版) ... Read More
独創哲学のメニュー決定
8月6日と9月21日に「独創哲学の仮メニュー」を段階的につくってきた。ようやく仮ではなく「本メニュー」ができた。私の生きる残り時間から逆算しても、このメニューが根幹的決定版になる。もちろん枝葉の箇所は流動的で、変更する可能性が高い。柔軟性を失わないようにしたい。 当サイトのメインコンテンツである「人類哲学の独創」に、『人間原理論』としてメニューをつくった。... Read More
経験よりも体験
【人類哲学の独創】ー『人間原理論』の核心部分の基本設計は十分にできたけれども、そこから派生する各論については今日もだいぶ変更した。思考や思想、意志、倫理なども各論となるので、これらを原理論全体のどの階層のどこに組み込んでいくのかについて、毎日が試行錯誤の連続である。 そうして真剣に考えていると、気づくことが幾つも生まれてくる。まず、ChatGPTが私にとっ... Read More
『人間原理論』の建設開始
私のライフワークの一つでもあり、当サイトのメインテーマでもある「人類哲学の独創」=『人間原理論』の大枠が固まった。ページリンクも構造化できたので、あとはどんどん書いていくのみ。修正が入るにしても構造の基本設計に大きな変更はない。構造設計ができたことで原理論の独創については半分できたも同じ。なにしろ無謀なほどに膨大な範囲を網羅する野心的なプロジェクトだからね... Read More
閑話
個人の観念世界についての探究は、実在世界の原理がどうなっているのかとリンクさせて考察する方法と、切り離して考察する方法がある。実在世界は人類文明が自然科学の分野を発展させたことによって、大きく信頼性を高めることになった。実在世界にかんしていえば、今や自然科学をエビデンスとして使われていないロジックは、使っているロジックと比較すれば、圧倒的に信頼度が低下する... Read More
サイト雑感
前の記事で「人類哲学の独創」についての最新MENUをアップした。MainTitleとSubTitleを決めた。構造原理における認識と表現とのあいだに「欲求」を加えた。この原理の中核は意志がどのようにして生成されるかにある。 それにしても、1年9か月ぶりに復活した断想7月24日から8月30日までの記事を再度読んでいくと、自分でいうのもなんだが充実している。概... Read More
独創哲学の仮メニュー/2023年9月版
先月8月6日に作った仮メニューをブラッシュアップした。1か月半も経つと明らかに変わる。3の各種理論については暫定的な項目なので、今後、大きく変わる可能性がある。1の構造原理と2の意味原理については、ほぼ確定的。 **************** 『人間原理論』 The Theory of Humanity --〈哲学的探究からの独自の洞察と創造知〉-- O... Read More