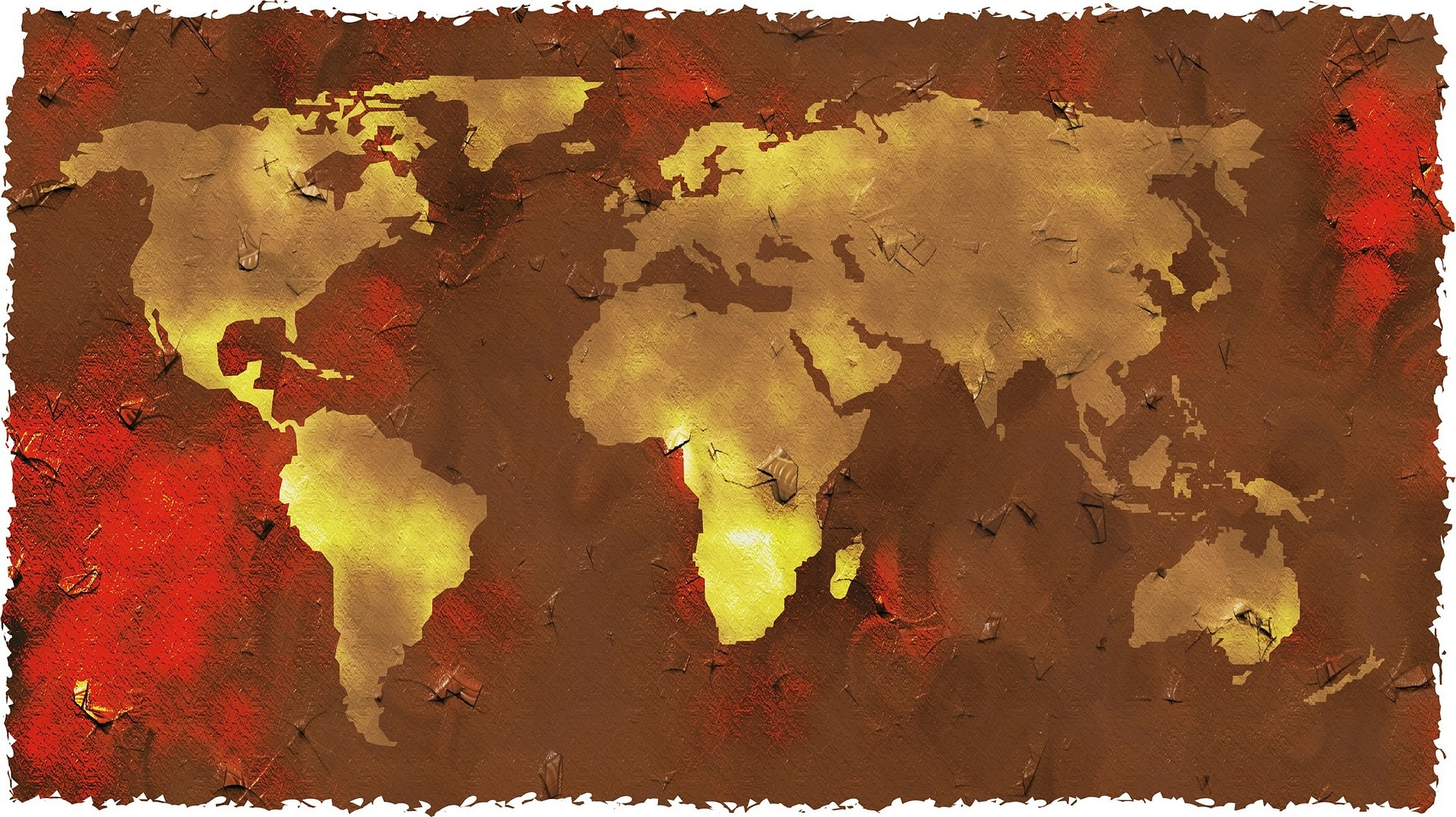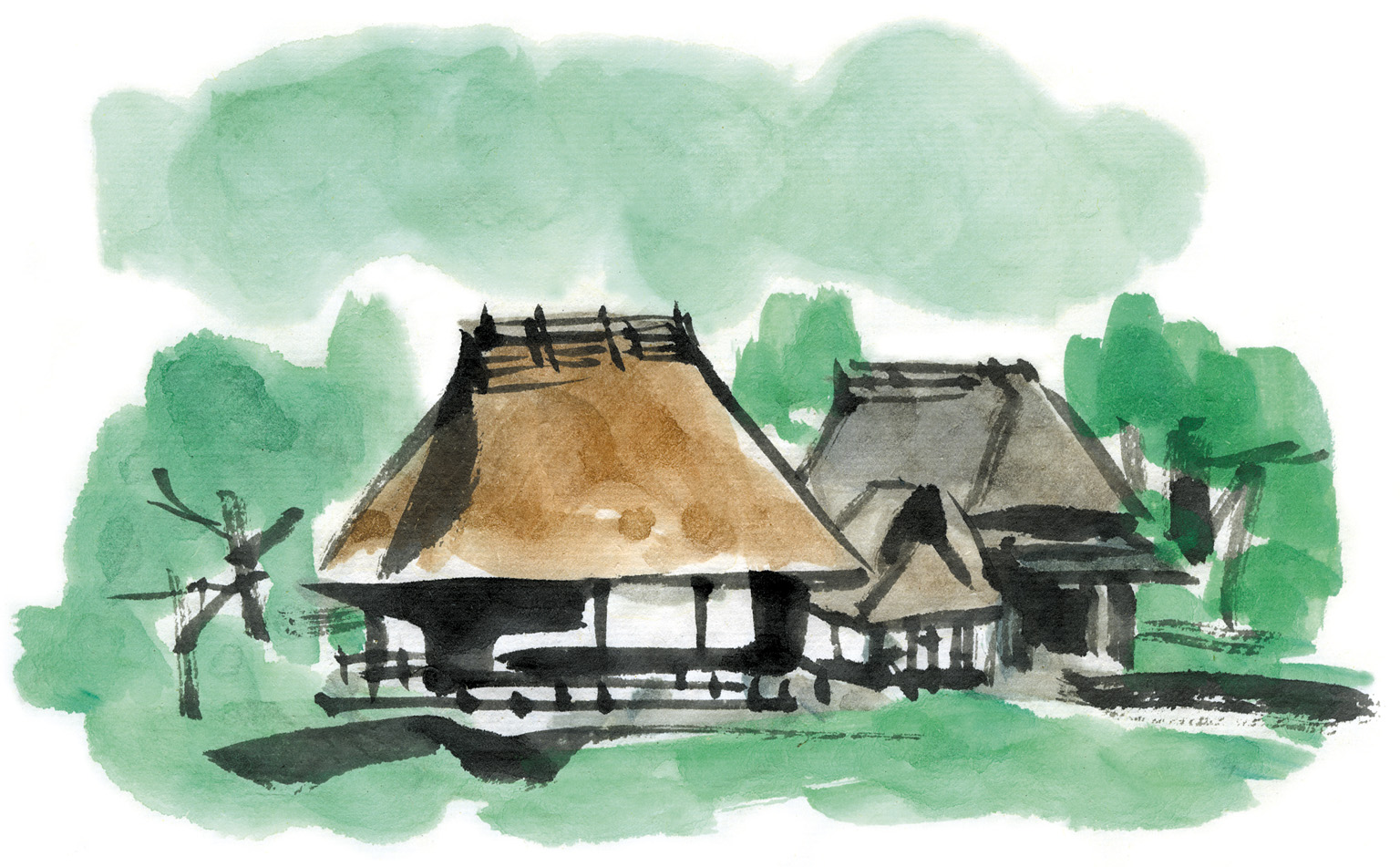「愛してる」 小林麻央さんの最後の言葉を海老蔵さんが公表したとき、胸が熱くなったかたが多かったのではないかと思います。私もそのひとりです。 私の世代では「愛してる」は世間のそこらじゅうに溢れていて、言葉にするにはちょっと照れくさいながらも、エーイ言ってしまえ!で言える言葉になっていました。おそらく団塊の世代の人たちまでは、歯の浮くような「愛してる」を、口か... Read More
「日本」という個性(1)
寒さには弱いけれど暑さには強いと自信をもっている私ですが、一昨日と昨日の暑さにはわずかに頭痛も覚え、体から熱さが引いていかない自覚があって、ムムムと思っていたのですが、久しぶりに昨夜から今日にかけて13時間ほど睡眠を摂ってスッキリしました。我ながらよく眠ります。悪い奴ほどよく眠るらしいし。 さて。 「多様性を認める地球人類」というテーマが、一... Read More
きよきあかきこころ―純日本思想
『古事記』や『日本書紀』に見られる「清(きよ)き明(あか)きこころ」について、私はこの心が日本人の原点であると考えています。そして何よりも大切にしています。 清き明きこころを実践できているかどうかと自問すれば、まだまださっぱり駄目なのですが。 この言葉の中には、純粋な日本人の哲学が凝縮されて詰まっているように思います。 端的に言えば、「きよきあかきこころ」... Read More
美しさを看(み)て、心が観(み)る
今年の3月は6年ぶりに寒い日が続きました。桜の木はそんなことなど意に介せず、花をつけていきます。 日本人は、春の桜にさまざまな心情を重ねます。美しさを感じとる感性が歓ぶ。そこから一歩踏み込んで情を混入する。わが身と重ね合わせることもある。しみじみとしてくる。 風情。情趣。 いま桜 さきぬと見えて うすぐもり 春に霞める 世のけしきかな &nb... Read More
「教育勅語」に縛られるな
日本の最高峰の議会である国会では、連日のように非建設的なワイドショー的話題に多くの時間が割かれていますが、いい加減にしてほしいと思います。 そのなかで出てきた「教育勅語」のお話。 稲田防衛大臣はどうやら、「教育勅語を復活させて道義国家を目指すべき」というふうに考えているようです。私的には、国難の際には天皇の臣下として皇道を守れという文言は憲法... Read More
「天」について
西郷隆盛は「敬天愛人」を座右の銘としました。 天を敬い人を愛するという、短く単純な教科書的意味でとらえて間違いはないのですが、天を敬うとはどういうことか、天とはなにか、人を愛するとは博愛主義なのかと、いかようにも掘り下げることができます。 『老子』でも『論語』でも、並んでいる漢文字は少ない。その少ない漢文字をどのように訳すかは、書き手の文脈だけでなく、読み... Read More
おのずからは心を尽くすことを求める
今日は昨記事のつづきです。「おのずから」について、相良亨(倫理学者 1921-2000)の著書より引用しつつ考察してまいります。 「おのずから」は、日本人の形而上にかかわる思惟の根底にあるものとして、さらに、本格的に考察されなければならない問題である。(東京大学出版会版 相良亨著『日本人の心』増補新装版) 相良は私のような心理分析からのアプローチからではな... Read More
日本人のしなやかな覚悟
今日は新しく作った「桜の人モード」で書きます。 昨日の記事で私は、捨て身の覚悟でと書きました。大袈裟に言えば死の覚悟ですが、日本に連綿と受け継がれてきた文化には、「思いきる覚悟」「美しく散る覚悟」「いさぎよい覚悟」「あきらめの覚悟」などいろいろとあって、一つの真理として「覚悟のすがた」を限定せず、しなやかに使いわけてきたのが日本人だと思うんですね。 『葉隠... Read More