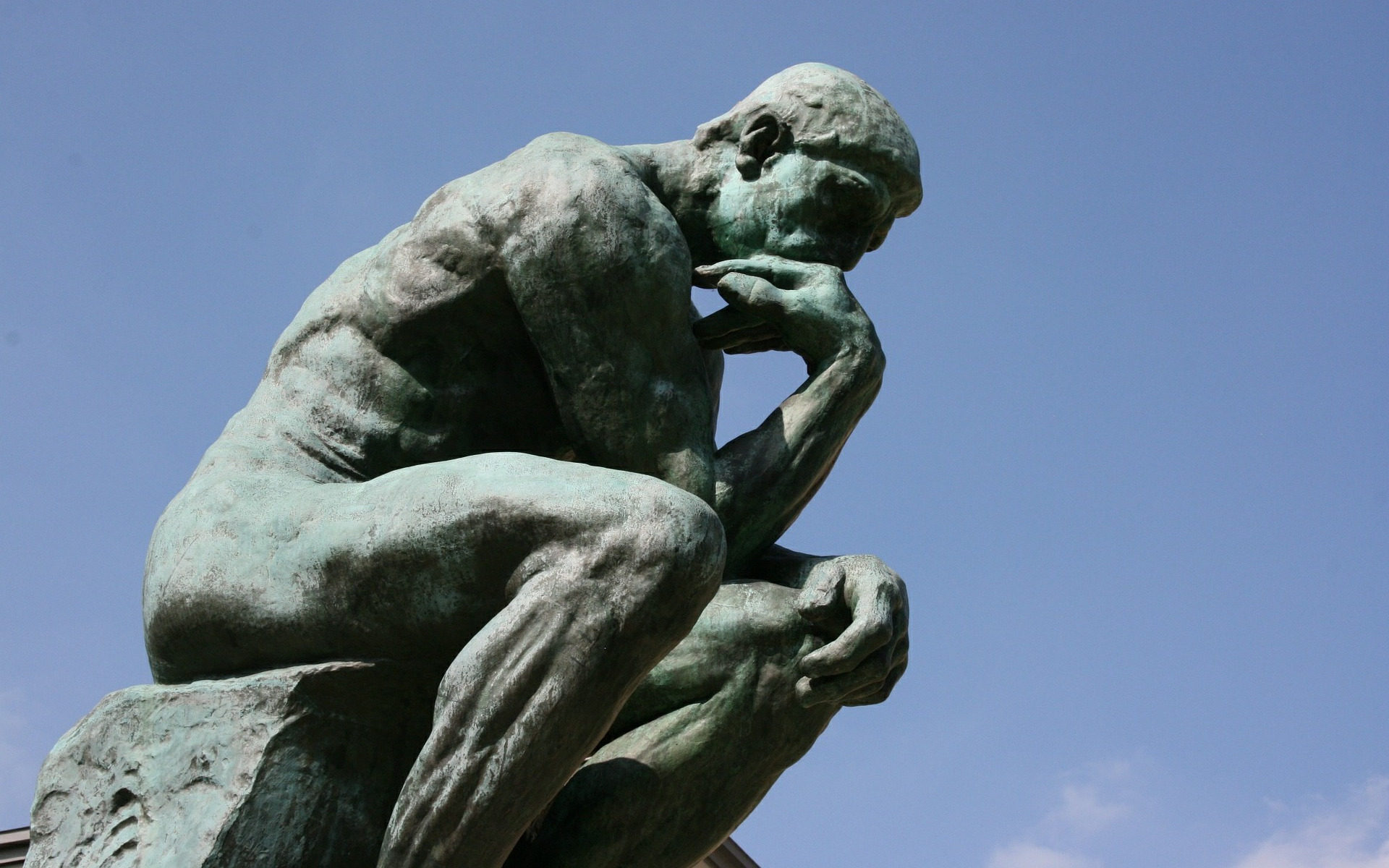小学6年生の5月、児童全員にカーネーションが学校から配られた。赤いカーネーションを子供から母親に贈る年一回の恒例行事だ。クラスひとりひとりに配られる。40人のうち39人に赤いカーネーションが、1人に白いカーネーションが担任教師から渡された。白の1人は私である。 前年の7月30日に母は35年5か月の短い人生に幕を下ろした。美容室を経営していた彼女の夢は日本一... Read More
星の王子さま(5)―Secret World
今回の星の王子さまシリーズは、この記事をもってラストとします。最後にとても大切なことに気づきました。 星の王子さまが自分の星に帰っていったあと、こう書かれています。少し長文になりますが引用します。 こうして、いまではもちろん、もう六年が経った・・・・・・ぼくはこれまでこの話を、一度も語ったことがない。 (中略) いまでは、いくらか悲しみが和ら... Read More
星の王子さま(4)―Solitude
(2)では Only One に触れたが、今回は角度を変えて「孤独」というテーマをとりあげる。『星の王子さま』の作品全体に感傷的な情緒を感じる人が多いかと思う。翻訳者が作品に寂しさを感じ感傷を意訳に織り交ぜている面もある。ユング派心理学者のM.L.フォン・フランツもその一人で、彼女は作者のサンテグジュペリについて次のように述べている。 一般にある種の残忍さ... Read More
星の王子さま(3)―Creativity
地球上の〈ぼく〉と星の王子さまは、飲み水を切らし砂漠の中の井戸を求めて歩き続ける。日が暮れて夜になってしまう。 「星たちは美しいね、見えない一輪の花のおかげで・・・」 「もちろん」とぼくは答えた。そして話すのを止めて、月光の下の砂の皺(しわ)を眺めた。 「砂漠は美しいね・・・」と王子さまはつけ加えた。 まさしくそれは本当だった。ぼくはずっと砂漠が好きだった... Read More
星の王子さま(2)―Only One
今日の記事では星の王子さまの核心にいきなり踏み込む。 表題の『Only One』でなんとなく解る人はいるに違いない。しかしそのなんとなく解った人の期待を私はたぶん裏切る。 本題に入る前に、書を味読する際には一つの視点から理解しようとする方法と、多数の観点(視点ではなく)を混在させながら感じる方法とがあることを確認しておく。 『星の王子さま』で... Read More
星の王子さま(1)―Prologue
『Le Petit Prince (星の王子さま)』 Antoine de Saint Exupéry サンテグジュペリ(1900-1944)作 1943年に出版されたこの書は現在、200か国以上の言語に翻訳され、世界的なロングセラーとして多くの人たちに愛読されている。日本語版も20社を超える出版社から刊行されており、それぞれの邦訳を楽しむこ... Read More
先賢とのおもしろ対話
昨日記事では「笑いながら哲学する」をテーマにニーチェをいじりましたが、今日は、わたし流の先賢との対話をおもしろく綴ってまいります。 上の写真は「考える人/ロダン」でありますが、やはりどうしても、トイレの最中に考えるふりをしているだけなんじゃないかという不安がよぎります。不安って?(苦笑) なんか哲学だとか何とか学だとかという学問っぽい書を読むときって、みな... Read More
ニーチェの茶目っ気ぶりご紹介
ニーチェをよくご存知ない人は、ニーチェと聞くとどういう想像をされますか? 哲学者で気難しい感じの人、天才と狂人は紙一重で遂に気が狂ってしまった人、『ツァラトゥストラはかく語りき』での「超人」を発明した人、よくわからない人(苦笑)などでしょうか? いえ、私もそれほど詳しいことは知らないのですが、ブログでちょくちょくニーチェを引用している手前、今... Read More
大海にひとり
何日も陸地が見えない北太平洋の海にひとり、船で旅をしているとすると、いったいどういう心境になるんだろう。 おだやかな海ばかりではないし、船底と鯨が接触するかもしれないし。 子どもの頃に『海のトリトン』っていうアニメがあって、歌詞がよかったんだ。知ってる人いるかな? 水平線の終わりには~、虹の橋があるのだろう~ 水平線ってロマンチ... Read More
削られて
人とは、彫刻のようなモノなんだ 何かを始めて 失敗して挫折して 削られて削られて やっと芯の綺麗な形が顔を出す だから やるからには 全力でやれ 全力でやって 恥をかけ そして 何かを成して ようやく少し見えてくる いい言葉だなあと思います。 削られないと、むきだしになってこない何かがある。 その何かって、自分では気づけないものなのですが... Read More